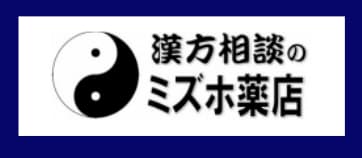三焦空間の気の流れと脈内の気の流れについて
2016年05月22日
今日も書籍を読むのに飽きてきたので、気ままにブログを更新します。
前回のブログにも書きましたが、五臓六腑、四肢、百骸、肌膚をつなぐのにとっても便利な三焦ですが、この三焦には衛気が巡って、各器官の隙間や表面、肌膚の間、肌の表面を滋養しているのですが、その1つに肌の表面や、その外側の空間をじんわり暖めながら、外からの外敵から身を 守る役割があります。
中医学の病機の中に表虚不固という病機があるのですが、このような方は、その肌の表面の外側のバリアの力が弱く、かぜをひきやすい、冷房に弱い、冷気にあたるとうすい鼻水がでる、よく寝汗をかくや、人より汗っかきなどの症状が現れることがあります。
このような方は、玉屏風散や防已黄耆湯、牡蛎散、桂枝加黄耆湯など、その人の具合によって方剤を選び服用すると改善します。
話がづれましたが今日のブログの本題に戻すと、三焦空間には衛気という気が循っていて、脈の中には営気という気がめぐっているのですが、この気のめぐりかたの違いを私なりに勝手に想像しているので書きたかったのです。
《素問・痺論》に「衛は水穀の悍気なり、その気は標疾滑利、脈に入ることあたわざるなり、ゆえに皮膚の中、分肉の間を循り、肓膜を燻じ、胸腹に散ず」
という条文の中に「悍気」や「標疾滑利」という語があり、何やら早く気が循りそうなイメージですが、私的には衛気の循り方は脈内を循る営気に比べ、安静時は4分の1の速度で循っているものだと考えています。
私が考えているイメージは、呼吸の速度と共に衛気の循環は連動しており、息を吐くときには身体の外側に衛気が出ていき、吸うときに身体の内側に入っていき、風によって動く霧みたいに動く、モワーて感じです。
(肺が気を主る事と腎が納める事も参考にしなければいけませんね。
そして腎が衛気の発生源ですので清気を吸い腎で衛気に替え、呼吸運動の吐く時に衛気がモワーと出ていくのです。)
それに比べ、営気は脈中を循るので、脈内は拘束されているのと、脈内の気は当然、肺の気を主る事を考えなければいけませんが、心は脈を主るので、心臓の鼓動の速さに影響を受けるので衛気より早いと考えております。心拍数のドン・ドン・ドン・ドンと共に営気は循っていくイメージです。
考えてみてください、だいたい人間の呼吸2回する間に(吸う・吐く・吸う・吐く)脈は正常な方で4回打つようになっています。そして衛気の循りは吸う、吐くで一循環に対して脈は1回打つ度に手先や足先にも血液は流れるし心臓にも戻るので一循環なので、衛気の循りは営気の循りの4分の1の速度なのです。
だから衛気は営気に比べゆっくり循るのです。
(*あくまでも私の個人的な意見です)
このような感じに勝手気ままにブログを更新しましたが、中医学を学んでいない方にはオカルト的な話にしか見えないでしょう。それ以前に現代人からしたら気の存在だけでもオカルト的ですね。
大阪の浪速区にあるミズホ薬店の店主。
お店にひきこもって漢方の勉強をしたり、漢方相談をしながら暮らしています。