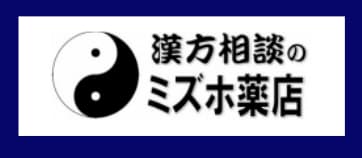中医学でよく出てくる「邪の湊まる(あつまる)所、その気必ず虚す」とは?
2025年10月16日
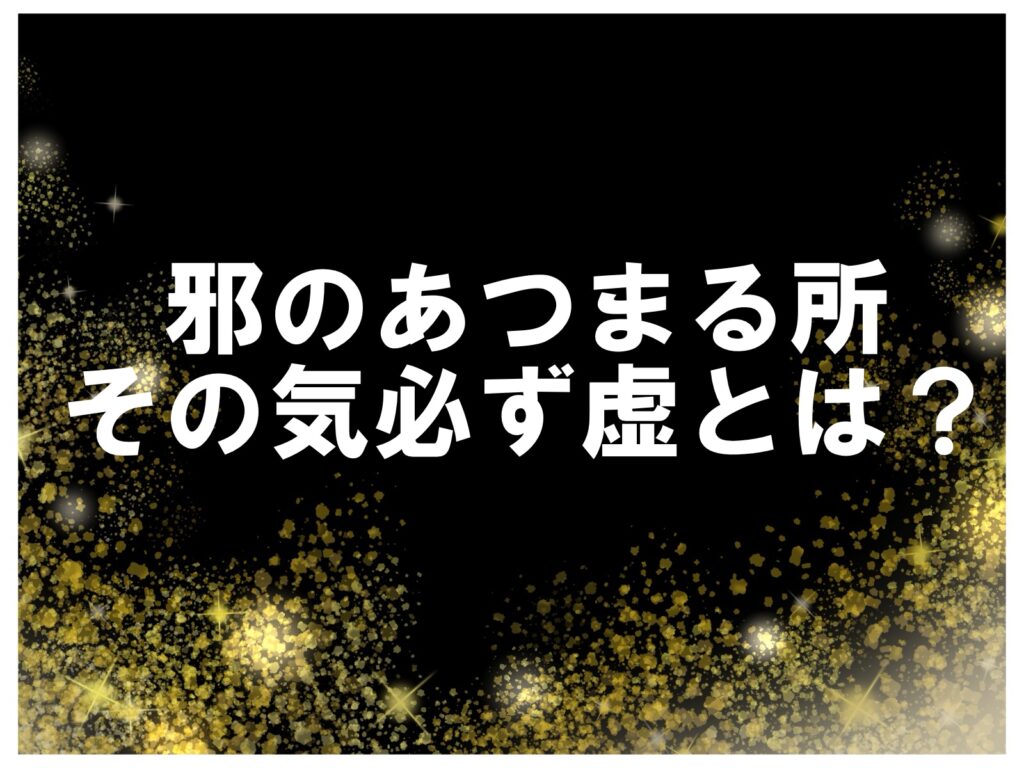
「邪の湊まる(あつまる)所、その気必ず虚す」という言葉が、中医学の古典である『黄帝内経素問・評熱論』にあります。
中医学の書籍によく出てくる有名な言葉で、この認識を深める事はご自身の病や健康状態を理解するのに役立ちますので、『中医理論悟変』瞿岳雲著を参考にして考えていきたいと思います。
邪とは具体的には外部要因である外感六淫(風・寒・暑・湿・燥・火)・内的要因の内傷七情(怒・喜・思・憂・恐・憂・驚)と、飲食の不節制や働きすぎや怠けすぎなどから引き起こされます。
気の虚とは、この場合の気は狭義の気(気虚や脾気虚など)ではなくて、正気の事を指しており、瞿岳雲氏は『中医理論悟変』において整体虚・局部の虚・暫時の虚の3つをあげています。
この3つの虚を書籍から引用しながら、解説を加えて理解を深めていきましょう。
①整体の虚
人体の陰陽・気血のいずれかのもしくは複数の全身性の虚弱状態があります。
よく中医学で使われる陰虚・陽虚・気虚・血虚・陰陽両虚などで、これらの虚の原因として、先天の気の不足・後天の不養生・病中病後・老化の4つがあげられます。
②局部の虚
臓腑や経絡・身体の各部などの特定部位の虚損を指します。
脾気虚・脾陽虚・心血虚・肝陰虚・上虚・下虚・経絡の虚などで、これらの局部の虚から全身に及ぶ事があり、また逆に全身から局部の虚がおこる事もあります。
例えば、皮膚病がおこっている時に、体表の虚に乗じて邪気が侵入しておこった場合に慢性化してしてしまい、かゆみや炎症に長期間悩む事により、睡眠不足や落ち込み・イライラが続く事で、全身の虚のつながるような状態です。
またその逆で飲食物の不節制・精神的ストレスの持続・働きすぎなどが引き起こす、全身の弱りから、体表の一部の皮膚に湿疹や蕁麻疹などの病変をきたす場合です。
①整体の虚で森をみて、②局部の虚で木をみる。
中医学での実際の臨床では、このふたつの視点を持たなければ、高い臨床効果を上げる事はできません。
③暫時の虚(ざんじのきょ)
暫時の虚とは一時的に生じる虚の事を指しており、過労や怠けすぎ・食べ過ぎなどにより、一時的に病に対する抵抗力が低下した隙をついて、邪気が侵入することによって病が生じる場合です。
日頃から心身がじょうぶな人でも、一時的な弱りをついて邪は侵入してくるので、何事もやりすぎは控えて、ほどほどにしておく必要があります。
また感染力が高いウイルスに対して、マスクや手洗い・うがいなどで予防できていた事に対して、無頓着にした結果、感染してしまった場合も、このパターンに属するでしょう。
①整体の虚・②局部の虚・③暫時の虚の3つの虚を理解する事により、虚というものの理解も深まったと思います。
また上記あげた邪の種類(外感六淫や内傷七情など)は、今回のブログに詳細は書きませんが、気になる方は、ネットで検索しても出てきますので調べてみてください。
次に「邪の湊まる所、その気必ず虚す」の理解として、明代の名医である張景岳の著書『類経』や、『内経講義』(→現代中医学の教科書の認識でOK)では、生体の虚があるから邪が侵入するという認識であるが、『中医理論悟変』の著者である瞿岳雲氏の考えでは、呉又可の『温疫論』の疫病の話などの例をあげて、強力な邪であれば、生体の虚がなくても集まった場所で消耗・戦闘が起こり、生体の虚を引き起こす事があるので、以下の2方面からの認識が必要であると説いています。
- 生体の虚から邪気が侵入して発病するケース
- 邪気が強力なので生体の虚がないのに侵入して虚を作り発病するケース
この考えは瞿岳雲氏だけではなく、昭和に活躍された山本巌氏の『東医雑録』にも書かれており、その流れをつぐ人たちにも受け継がれており、現在のスタンダードな考えになりつつあります。
以上、はるか昔に書かれた古典である黄帝内経の一文の「邪の湊まる所、その気必ず虚す」でありますが、中医学を勉強したり、実際の臨床では外せない言葉ですので、よろしければご参考にしてみてくださいm(_ _)m
参考文献:中医理論悟変
大阪の浪速区にあるミズホ薬店の店主。
お店にひきこもって漢方の勉強をしたり、漢方相談をしながら暮らしています。