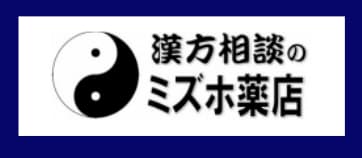内風について
2025年10月09日
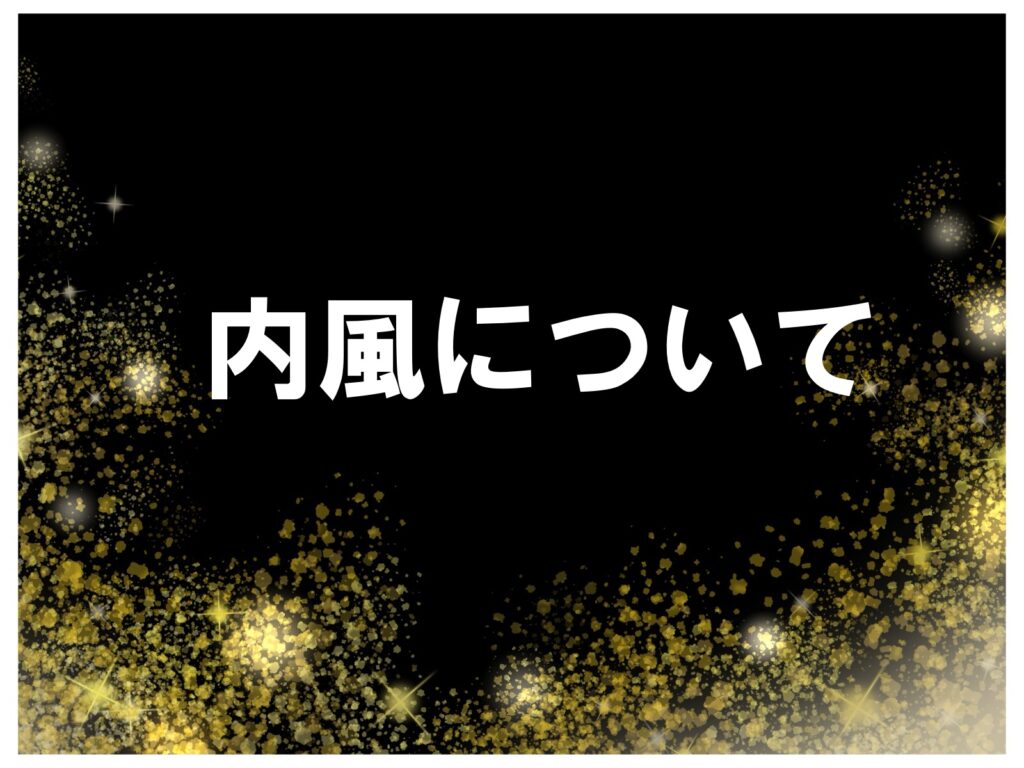
病院で検査しても原因がわからず、めまい、筋肉の震えや痙攣といった症状にお悩みの方に対して、中医学ではこれを「内風証」と捉え、それに対応する漢方薬を服用していただくと、症状の改善がみられることがあります。
今回のブログはその「内風証」について、専門書を引用しながら、やや専門的な内容を書いていきたいと思います。
『中医弁証学』柯雪帆著 肝風内動証
「本証は内風証のひとつであり、動揺現象(ふるえ・ふらつきなど)、目眩・痙攣などの症状をともなう病証である。肝腎の極度の陰虚により陽を制御できない場合、血が筋をうまく栄養できない場合、肝陽の昇動をまったく制御できない場合などに起こる。
『素問』至真要大論には『諸風晫眩皆肝に属す』とあるが、これは肝風内動証の病機を概括したものである。本証の根本的な病機は肝腎の陰液の損傷である。肝腎陰虚を引き起こす原因の違いにより異なった症状、所見が現れる。よくみられるものとしては、肝陽化風・熱極生風・陰虚動風・血虚生風の4証がある。」
『風火痰瘀論』章真如著 風証論
「人体に対し最も害が大きいのが、じつは『外風』でなく、人体内部から発生する『内風』である。
では『内風』はいったいどこからやってくるのであろうか。『素問』至真要大論には『諸風晫眩皆肝に属す』とある。内風の起源は肝にあると『素問』は述べているのである。『肝風』という固定した呼称もこれを裏付ける。
さて『肝風』の発生には『肝陽化風』『熱極生風』『血(陰)虚生風』の3つの状況が想定されている。『肝陽化風』では肝陽が亢盛し、肝陰が肝陽を抑制できなくなった結果、風を生じる。『熱極生風』では高熱あるいは久熱(慢性的に滞留した熱)が肝経を焼灼し、そのため肝陰が損なわれ、肝陽が偏亢し、筋脈が栄養を失った結果、風を生じる。また『血(陰)虚生風』では肝(腎)の陰血が虚衰し、肝陽が亢盛した結果、風が生じる。
3者は臨床症状にそれぞれ特徴をもち、発病の起点に違いがあるものの、病機に関して見ると、ともに肝陽(気)亢盛およびこれと相対的な肝陰(血)不足が存在している。『内風はすなわち身中の陽気の動変なり』といわれる所以である。肝陽が制御不能に陥り、陽熱が亢盛すると風が生じ、暴れ回るのである。
外風と内風は互いに影響し合い、原因と結果としてリンクすることも多い。たとえば温病では、前期には外風による病原が主となるが、化熱により陰が焼灼された後期には陰液の消耗により内風が現れる。
このように、内風の原因はすべて陰血や津液の損傷から起こる。」
『中医証候鑑別診断学』第二版(姚乃礼主編)
証の鑑別についての大書である本書に記載されている証候(◯◯証)の数は、基礎証候から臓腑証候、傷寒証候、温病証候、耳鼻喉科証候などにわたり、その数はなんと483証である。証を専門的に研究した書といってよいであろう。その中の基礎証候である風証も確認しておこう。
「風証には外風、内風がある。外風は風邪を外感することによって起こる。風邪は六淫のひとつであり、陽邪に属し、外感疾病の原因のきっかけになることが多く、風寒・風熱・風湿・風燥などのように他の病邪を兼ねることによって発病する。風邪は多くは衛表(体表の防御機能)を犯し、肌腠、経絡を襲い、遊走性と多変性の特徴をもった症状を引き起こす。
内風は内生五邪の一つであり、すなわち風気内動あるいは肝風内動を指す。これは臓腑の機能失調や火熱熾盛、陰血虧虚などの原因から、陽気の亢逆変動により気血が逆乱し、筋脈が失養するために、動揺、めまい、抽搐(ひきつけ)、震顫(ふるえ)、麻木(しびれ)などといった、陰血が陽気を制御できなくなった病理証候である。」
私の訳がよくないのかもしれないが、他の書籍に比べてわかりにくい。
『中医病因病機学』宋鷺冰著 風気病機・内風病機
「『素問』陰陽応象対論篇は『風勝てばすなわち動ず』と述べている。この一節にみられるように、内風病機には動揺・眩暈などの病理変化が含まれる。また、頭暈眩暈、四肢の抽搐、四肢や皮膚のしびれ、震え、硬直、突然昏倒する、人事不省、口眼喎斜、半身不随などの症状をともなう。
その病理は、筋肉・眼・精神の異常である。これは肝が血の貯蔵を主り、眼を精で潤し、筋を気で養うからである。また肝は魂を内蔵し、謀慮を主り、精神活動と密接に関連しているからである。
したがって、内風を生ずる主因は肝にある。肝風が生ずるのは、陰虚・血の不足のために風陽が上昇して筋脈の潤いが失われるからである。また陽熱が強すぎると、肝経を焼いて内風を煽動する。さらに、一部には陽気不足から筋脈の温煦作用が失調して発生するものもある。」
以上、4書の内風の病機に関する記述を引用したが、内風の原因として「陰液(陰血・津液)の損傷」が共通して挙げられている。なお『中医病因病機学』のみ、内風の原因として「陽気不足による筋脈の温煦機能の失調」も指摘している点は、頭にとどめておくとよい。
脾虚による内風
脾土が虚寒すれば、陽気が四肢の末端まで届かないため、手足の筋脈が温まらず、気も津を散布できない。すると筋脈は潤いを失い、風気が発生し、拘急・抽搐などの症状があらわれる。
日本人は胃腸が弱い人が多く、梅雨から夏にかけて湿度が高い季節を過ごすため、脾虚から起こる内風証を治療する際に半夏白朮天麻湯や釣藤散などが多用される。したがってその病理を深く掘り下げて認識しておく必要がある。
この病理は、陳潮祖著『中医治法与方剤』に詳細に記されているので、そちらを確認しておこう。
『中医治法与方剤』には、陰液(陰血・津液)の損傷からくる肝風内動証のほかに、風痰阻滞証と土虚生風証が記載されている。どちらも脾の運化機能の失調により起こるが、風痰阻滞証は脾の運化失調から痰が形成され、血脈外の三焦に停滞して衛気の運行を妨げ、筋膜を温め滋潤できず、筋膜のけいれんやふるえなどを引き起こす。
この病機では、主原因は「肝陽化風証」「熱極生風証」「血(陰)虚生風証」などの陰液損傷ではなく(厳密には熱極生風証は熱邪であるが)、脾の運化失調による痰の形成である。よって、半夏白朮天麻湯や釣藤散で脾の運化を整え、痰を除去し、生成を防止する必要がある。そこに天麻や釣藤鈎などの平肝熄風薬を併用して肝を鎮め、筋膜のけいれんやふるえを改善していく。
土虚生風証は、胃腸かぜや胃腸の弱りにより下痢や嘔吐が続き、津液を失うことで手足のけいれんが起こる状態である。この場合も脾の運化失調を治し、下痢と嘔吐を治すことが不可欠である。
内風証を弁証論治する際には、「肝陽化風証」「熱極生風証」「血(陰)虚生風証」に加えて、脾虚から起こる「風痰阻滞証」と「土虚生風証」も頭に入れて臨床に臨む必要がある。
もっとも、実際の臨床ではうまく言語化できない病態も少なくないが、中医学をベースに誰かと共有しながら治療する場合は、用語が指す意味を事前に確認しておくことが重要である。
引用書籍
『中医弁証学』柯雪帆著 兵頭明訳 東洋学術出版社
『風火痰瘀論』章真如著 渡辺賢一訳 東洋学術出版社
『中医病因病機学』宋鷺冰著 柴崎瑛子訳 東洋学術出版社
『中医証候鑑別診断学』第二版 姚乃礼主編 人民衛生出版社
『中医治法与方剤』第五版 陳潮祖著 人民衛生出版社
大阪の浪速区にあるミズホ薬店の店主。
お店にひきこもって漢方の勉強をしたり、漢方相談をしながら暮らしています。