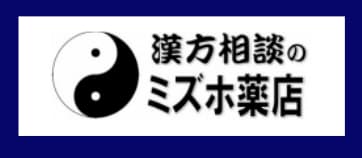逆流性食道炎の漢方での考え方と漢方薬について
2022年11月28日

逆流性食道炎とは
逆流性食道炎は胃や十二指腸の内容物が逆流することにより、食道の粘膜に炎症をおこす病気です。
逆流性食道炎をひきおこす原因は、胃と食道の連結部分に下部食道括約筋(LES)といわれる筋肉があり、胃の内容物を逆流しないようにしていますが、下部食道括約筋(LES)働きの低下により胃や十二指腸の内容物が逆流して、食道の粘膜に炎症がおこります。
症状は胸やけ・呑酸(食後・夜間・前屈位時にみられます)・胸痛・せき・喘鳴(呼吸する時にヒューヒューやゼーゼー)・咽喉頭の違和感・耳痛・声がかれるなどの症状がみられます。
漢方での逆流性食道炎の考え方
逆流性食道炎をひきおこす原因は、食生活の乱れ、味の濃いもの・油もの・辛いもの食べすぎ・お酒の飲みすぎによる脾胃の機能低下による痰湿の発生と、胃の気逆による消化液の逆流症状です。
また精神的なストレスの影響で肝気が滞ると脾胃の働きを阻害しますので、不快な症状が悪化します。
また肝気が滞り気鬱傾向が続くと胸部や胃部に熱をもち、脾・胃・肺の陰を損傷したり、痰湿と結びつく事により熱痰(ねつたん)・湿熱(しつねつ)という邪気になり、逆流性食道炎の病態を複雑化させます。
治療法は
- ①脾胃の機能をもどす
- ②肝気を整える
- ③熱を冷ます
- ④肺・胃・脾の陰を養う
①は逆流性食道炎を漢方薬で治療する時の必須条件になり、②・③・④の状態を考えて治療法を決定し、適切な漢方薬を選びます。
逆流性食道炎の漢方薬
逆流性食道炎で使われる漢方薬の一部を紹介します。同じ逆流性食道炎でも色々な漢方薬を使うのだなというイメージをもってもらえると良いです。
六君子(りっくんとう)『医学正伝』
【構成生薬】人参・白朮・茯苓・甘草・半夏・陳皮・生姜・大棗
逆流性食道炎の消化液の逆流症状にともなう胸やけ・呑酸・胃の不快感にあわせて、食欲がない・食べると胃がもたれる・お腹をこわしやすい・疲れやすく食後に眠くなるなどの症状があります。
小さい頃から胃腸が弱く食べすぎてしまうと、胃がもたれたりお腹をこわしやすく、食べても栄養になりにくく太れなかったり、逆に痰が増えて咳や後鼻漏になったり皮膚炎の症状でお悩みの方もいらっしゃいます。
半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)『傷寒論』
【構成生薬】半夏・黄芩・乾姜・人参・甘草・黄連・大棗
逆流性食道炎の胸やけ・呑酸の症状に、みぞおちに何かつかえているような感覚がありますが、実際にさわってみるとかたくはなくやわらかいです。調子が良い時は食欲があり、そこそこ食べれますが、食べすぎた時はお腹がゴロゴロと鳴り軟便や下痢になりやすいです。
神経が高ぶりやすい方が多く、睡眠の質が悪く夜中に何度も目が覚めたり、飲食物とは関係なく仕事のストレスなどでゴロゴロとお腹をこわす方もいます。胸や胃に熱がこもりやすいので、胃腸の調子が悪くなると口臭が発生したり口内炎・口のまわりに膿をもったデキモノができる事もあります。
黄連湯(おうれんとう)『傷寒論』
【構成生薬】黄連・甘草・乾姜・桂枝・人参・半夏・大棗
黄連湯は半夏瀉心湯から黄芩を抜き、桂枝を加えて黄連の量を増やしています。胃熱や神経を鎮める黄連を増やして桂枝を加える事により、黄連の働きを血脈に入れる作用を強めている事から、黄連湯があう方は半夏瀉心湯に比べて胃や胸の痛み・呑酸症状が強い傾向にあります。
お腹から下半身が冷えやすくのでお腹がゴロゴロとなりやすいのは半夏瀉心湯と同じなのですが、半夏瀉心湯よりさらに神経質な方が多くストレスからのぼせや頭痛がおこす事もしばしばあります。
大柴胡湯(だいさいことう)『傷寒論』
【構成生薬】柴胡・黄芩・半夏・生姜・大黄・枳実・芍薬・大棗
逆流性食道炎の胸焼け・呑酸に吐き気の症状が強い事が多いです。大柴胡湯も半夏瀉心湯と同じくみぞおちの不快感があり、何かつかえている感じがありますが、実際にさわっってみるとかたくなって事が多く、触られるの極端に嫌がる傾向にあります。かたくなっていない方もいますが、その場合でもピッタリとした衣類でしめつけられるのが嫌であったり、窮屈さを嫌う方が多いです。締め付けられる感覚出た時に、咳払いをするクセがある方もいらっしゃいます。
まるで食欲スイッチがあるかのように食欲にムラがある事も多く、まったく食べれない時があれば気分が良い時は食欲が旺盛になったります。お腹は冷えに対して弱くなく便秘傾向です。
茯苓飲合半夏厚朴湯(ぶくりょういんはんげこうぼくとう)『本朝経験方』
【構成生薬】茯苓・白朮・人参・陳皮・枳実・生姜・半夏・厚朴・蘇葉
胃のあたりに水がたまったような感覚ある方の逆流性食道炎に効果があります。水分をとってもうまく吸収していない感じで気持ち悪くなり、逆流性食道炎の症状が強くなります。
また自分の身体への不安感が強く、「逆流性食道炎以外の病気じゃないか?」と心配になりすぐに薬局で相談したり、病院に行って検査をしてもらう事が多い傾向にあります。のどに何かつまったような感覚が出る方もいます。どちらといえば色白でやわらかなイメージを持った方が多い印象です。
竹葉石膏湯(ちくようせっこうとう)『傷寒論』
【構成生薬】竹葉・石膏・麦門冬・半夏・人参・甘草・粳米
胸やけや呑酸がある時に胸部や胃部の熱感や口の乾き感が強く、せきが出るような逆流性食道炎の方に効果があります。せきは痰がからむような咳で、最近では慢性上咽頭炎の方で逆流性食道炎もあるという方に使うと、上咽頭の炎症の緩和と逆流性食道炎の症状の両方を緩和できる事もあります。
冷たい飲みものを好む傾向があり水分の摂取量も多く、全体的に乾いている印象があります。中には氷を口に含んだり、食べたくなるという習慣をもっている方もいらっしゃいます。
参苓白朮散(じんれいびゃくじゅつさん)『太平恵民和剤局方』
【構成生薬】人参・茯苓・白朮・甘草・山薬・白扁豆・蓮肉・薏苡仁・縮砂・桔梗
逆流性食道炎の胸やけの症状に加えて、食欲がない・食べると胃がもたれる・お腹をこわしやすい・疲れやすく食後に眠くなるなどの症状は、六君子湯に似ていますが、口の乾き・手足のほてり・便秘など熱をあらわす症状が出ますが、黄連・黄芩・大黄・石膏などの冷やす漢方薬を飲むと胃もたれしたり、頭痛がおこったりと悪い反応が出ます。
舌を見ると、舌苔がところどころ剥がれてまだらになっているのが特徴的です。
逆流性食道炎の漢方相談の実際
プロトンポンプ阻害薬(PPI)やH2受容体拮抗薬で効果があらわれる方が多いですが、不快な症状が残ってしまう方や無効な方もいらっしゃいます。
そのような方でも漢方薬を併用したり、まったく効果がない方は漢方薬に切り替えると改善する場合もありますが、逆流性食道炎だから六君子湯という病名で漢方薬を選ぶ場合には、なかなか効果を感じられませんので、きちんと相談して漢方薬の反応をみながら調整してくのが良いです。
大阪の浪速区にあるミズホ薬店の店主。
お店にひきこもって漢方の勉強をしたり、漢方相談をしながら暮らしています。