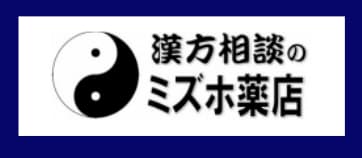かぜ・インフルエンザ・コロナの感染初期に漢方薬を効果的に使う方法
2024年05月21日
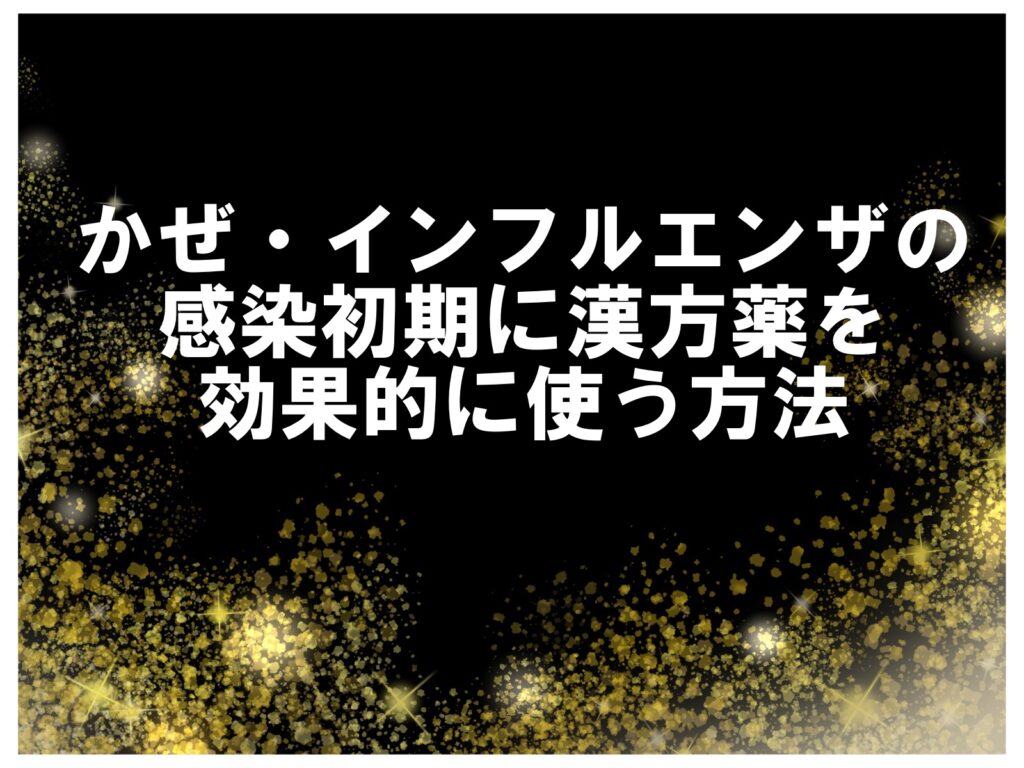
かぜ・インフルエンザ・コロナなどに感染した時に、漢方薬で治療する場合に初期対応が大切です。
かぜは万病の元と昔から言われるように、色々な症状をひきおこす慢性上咽頭炎やコロナ後遺症などもかぜがうまく治りきらずに、こじらせてしまった結果ともいえます。
今回のブログは、かぜ・インフルエンザ・コロナなどに感染した時に寒気がある感染初期に、麻黄湯や葛根湯・桂枝湯・荊防敗毒散・香蘇散などを使用しますが、効果的な使い方とその理由をご紹介いたします。
かぜ・インフルエンザ・コロナ感染時の悪寒について
かぜやインフルエンザ・コロナのご相談の時に、初期の方の場合は悪寒(背中にぞくぞく)とした寒気を訴えている方がいらっしゃいます。
漢方では体表に風寒の邪気が侵されたという表現をします。
その表現はあくまでも、患者のどこの場所にどのような不快症状が生じているかという言葉で表現しているだけですので、現代に生きる私たちからするとオカルト的に聞こえますが、あまり気にする事はありません。
悪寒がある時に使用する漢方薬とその目的
そんな時に使用する漢方薬は、麻黄湯や葛根湯・桂枝湯・荊防敗毒散・香蘇散などの辛温解表(しんおんげんひょうやく)と呼ばれる漢方薬を使用します。
辛温解表薬は、汗法・吐法・下法・和法・温法・清法・消法・補法の八法のうちの汗法に相当し、漢方薬を飲む事によって肺気の宣発作用を高めて体表にいる邪気を払うと言われています。
かぜやインフルエンザ・コロナにの感染初期に寒気がある時に、ただ漢方薬を飲むだけでは100%発揮することはできません。これらの漢方薬を飲むのはあくまでも汗法といわれるように汗を出すことが目的になります。
漢方薬だけで汗が出にくい時には、温かいお湯やスープなどを飲んだり・厚着したり・漢方薬の服用回数や服用量を増やすなどの工夫をする必要があります。
ただし汗が出た時点で、漢方薬の服用は中止するか変更する必要があります。
漢方薬をだらだら服用して発汗を続けていると、体の潤い成分である津液と元気の源である気が失われるからです。→この事からかぜもひいていないのに、予防で麻黄湯や葛根湯を飲むのは体に悪いと理解できますよね。
ウイルスや細菌に感染して体温が上がるのは、体の治癒活動を高めるためと考えられており、感染初期に寒気がして、体が震えるのは筋肉を痙攣させて熱を産生して体温を上昇させるためです。
ウイルスに感染した時に体が必要としている体温まで上昇すると、筋肉を痙攣させる必要がなくなるので悪寒はおさまります。そのまま体を温め続けると汗となって出ていき体温は上昇しません。
その状態を続けることによって、侵入して繁殖したはじめたウイルスを駆逐していきます。
辛温解表薬に麻黄湯・桂枝湯・荊防敗毒散・香蘇散などあるのは、感染したウイルスの種類や季節・住んでいる土地・体質・体調・薬との相性などによって使用する漢方薬が変わるからです。
汗をかかせるのに注意が必要な人
高齢者・心臓が悪い人・低血圧・神経過敏な人などの弱っている人は麻黄湯や葛根湯を飲まして汗をかかそうと厚着をさせると、心臓がドキドキしたり逆にしんどくなってしまうので注意が必要です。
そのような方々には即効性は期待できませんが、参蘇飲や香蘇散などのゆるやかなものでじっくりと治療する必要がああります。
以上がかぜ・インフルエンザ・コロナの感染初期に漢方薬を効果的に使う方法になります。
同じ漢方薬を飲むのにも、その漢方薬の治療目的を理解して使用すると効果が断然に変わりますので、よろしければご参考にしてください。
ただし、初期に悪寒がない場合は今回の辛温解表薬ではなく温病学の理論に基づいて作られた、辛涼解表薬を使用する必要がありますのでご注意ください。
大阪の浪速区にあるミズホ薬店の店主。
お店にひきこもって漢方の勉強をしたり、漢方相談をしながら暮らしています。