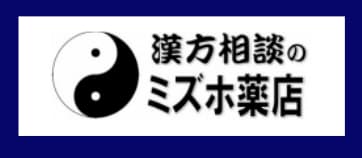痰や鼻水(前鼻漏・後鼻漏)の色や粘りの強さの中医学の基本認識と例外
2024年05月18日
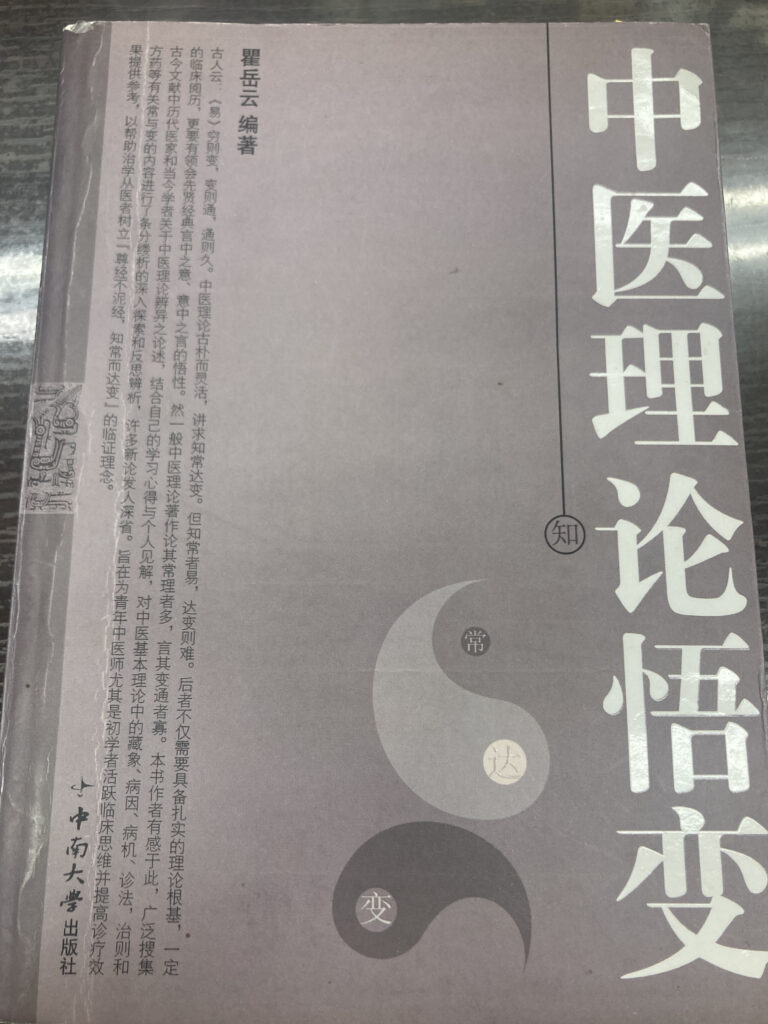
痰や鼻水(前鼻漏・後鼻漏)を漢方で治療する場合には寒・熱の判断は大切です。
寒・熱の違いによる使用する漢方薬は変わり、的確に判断しないと治療効果が出ないばかりか悪化させてしまいます。
中医学の診断基準は
- 痰・鼻水(前鼻漏・後鼻漏)が透明or白でさらさら→寒
- 痰・鼻水(前鼻漏・後鼻漏)が黄色く粘り気が強く→熱
になっています。
しかしすべてがそうでなく例外もあるという事を、中医師である瞿岳雲の著書である『中医理論悟変』の中に「白痰はすべて寒証ではなく、黄痰は皆熱ではない」という考察がありますので、今回のブログはそちらを意訳してご紹介いたします。(↓以下意訳になります。)
痰は肺から出て、痰の形は目で見る事ができるので証をたてる事ができます。
痰の色や質・量を観察する事は、中医学の望診や問診の大切な内容のひとつです。
弁証の意義において痰の色について論じると、一般的には痰の色が白いものは寒に属し、痰の色が黄いものは熱に属すると言われています。
しかしすべてがそうではありません。
例えば実際の症例をあげますと、黄い痰を排出する肺膿患者が、西洋医師の治療を1ヶ月ばかり受けてが治らないので、中医師の治療を求めて桔梗湯合千金葦茎湯を10日ばかり飲んだが、いまだに効果は出ませんでした。(→桔梗湯合千金葦茎湯は、肺を冷まして排膿を促す漢方薬です。)
その患者の痰を見ると黄色く濁っていましたが、口の渇きはなく、熱証の場合は脈が早くなるのですが、その方の脈は力がないゆるい脈で、あわせて舌は淡く、体はだるく、寒さが苦手で、小便の色は透明でよく出て、大便は軟便傾向などと、陽虚脾弱の症状が見られました。
よって治療方針の寒熱を入れ替えて、『金匱要略』の甘草乾姜湯と皀莢丸を考えをもとに、方剤を組みたて6剤を与えると著効し、さらに6剤を与えた後に、培土生金にもとづき理中湯加味で補肺化痰をすると治りました。『陝西中医、1986、4:181』(→甘草乾姜湯は肺やお腹を温める漢方薬で、理中湯はお腹を温める漢方薬です。)
清代の中医師の何夢瑶いわく
「痰の、昔の人は黄色でねばりけの強いものは熱、白くうすいものは寒、これは特に概略を言っているのであって、こだわりすぎるべきではない。
外感の病を例にあげると、傷風咳嗽、咳とともに痰が頻繁に出て、色はみな稀白であるので、誤って寒治をすると、多くは症状が悪化する。火は盛んになり胸をふさぎ、さらに咳はひどくなるが未だに痰は黄色く粘りけをもつ事はない・・・・これは内傷の病でも同じことである」
それでは、実際になぜ患者の証候が寒に属さないのに、その痰は白色になるのでしょうか?
痰は津液から生じて、熱に煮詰められることによってその色は黄色になりはじめ、痰の色は白から黄色になるのは転化の過程のひとつです。
痰の色はこの転化の過程の遅速と邪熱の強弱・来勢の緩急と、人体の津液耗損度およびその生化能力と関係しています。
臨床でよく見られる外感風熱証の身熱、口の乾燥、のどが赤く腫れて痛む、舌の色は赤く脈は早いなどは熱証の症状でありますが、咳して吐く痰は白色であり、この痰の色だけで寒証と判断すると、全身症状と合致しなくなります。
これはすなわち外邪を受けてからの時期が早いので、津液が熱を受けて痰になるといえども、頻繁におこる咳によって排出されるので留まる時間が短く、病の初期には津液も充実しているので、痰液はまだ粘り気をもち黄色くなることはないのです。
また人体の正気が駆邪外出の機転下において、病状の好転にしたがって痰の色は白〜黄色に転じる事が、しばしば咳が治る良い兆しのこともあるので注意が必要です。
清代の中医師である陳士鐸の『石室秘録』の説に
「病の痰は、必ず白色と黄白が現れるので、それ分析して明らかにするがよろしく、黄色が火が退こうとしているところで、白は火が盛んになっているなり。」
すなわちこれが指す事は、反って病が寒に属するものは、痰は黄色ねばりけをもつという事です。
このような事は実際の臨床でも見ることがあり、前述の病案もこの例であり、これはすなわち陽虚で水液の気化機能が失調して、水湿が留まる事によって痰になり、痰が同じ場所に長時間停滞すると気がつまり熱が生まれ、痰の色は黄色くなります。この場合の病の本は寒であり、その標は熱として現れます。
以上、瞿岳雲著『中医理論悟変』の中に「白痰はすべて寒証ではなく、黄痰は皆熱ではない」という考察を意訳させていただきました。
最近ではネットやSNSなどで漢方の選び方の情報を得ることができます。
痰や鼻水(前鼻漏・後鼻漏)などの分泌物の色や粘りの強さから寒・熱の判断も見かけることも多いですが、漢方での体質や病気の状態を判断するにはひとつの情報だけにとらわれすぎに、色々な情報を得た上で総合的に判断することが大切です。
大阪の浪速区にあるミズホ薬店の店主。
お店にひきこもって漢方の勉強をしたり、漢方相談をしながら暮らしています。