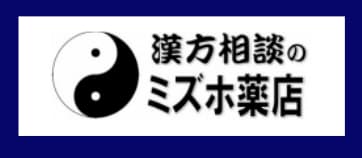脾陰虚と胃陰虚について(2)
2016年05月25日
引き続き脾陰虚と胃陰虚についてのブログを書いてきます。
確か、脾陰虚の状態のバリバリの土までいきましたね。
まずは、よく書籍に出てくるい胃陰虚から書いていきます。
「病機と治法」陳潮祖著 抜粋
(ちなみに原本は「中医病机治法学」になっており、病機の機の字が机になっており、初めなんで机やねんと思っていましたが、 何やら機の簡体字が机らしいです)
胃陰虚:胃の陰液虧損の病機
治法:益胃生津
本証の主症状は口の渇き・口唇の乾燥・咽喉の乾燥・舌質は紅で乾燥・胃部の疼痛・便秘などである。
脾は燥を喜み、湿を悪み、胃は潤を喜み燥を悪み、脾胃の運化に大過も不及もなく燥湿が互いに助けあっていると無病である。
素体が陰虚で胃陰が不足したり、熱病の後機で胃津が消耗し、津液が虚乏して上承できないてめに口の渇き・口唇の乾燥・咽喉の乾燥・舌質が紅で乏が生じ、胃を濡潤できず胃気が和降しないために胃部の疼痛がみられ、腸を濡潤できないと大便が乾燥し排便困難になる。
胃陰虧損は益胃生津液により津液を補充するのがよく、陰津が補充されると燥渋も自然に解ける。
養陰生津の沙参・麦門冬・玉竹・石斛・生地黄・玄参・西洋参・知母。梨汁・蔗漿などを主薬とし、他の薬物を佐薬として組み合わせて、方剤を組成し、養陰増液の効能を得る。
方剤例⇒麦門冬湯・加味麦門冬湯・益胃湯・五汁飲
この種の方剤の組み合わせでは、養陰して膩滞しないように注意すべきで、中焦を壅滞させ消化を妨害しないようにする必要がある。
例えば五汁飲は、五種の植物の自然汁で生津するが、生津して膩滞しないという用薬の特徴を持っている。
滋膩の薬物を用いるときは、脾津を輸転する薬物を加えて脾運を促進すべきである。
たとえば、麦門冬湯に半夏を用いるのは、生津と燥湿という相反する薬物の配合により相反相生の治療効果を挙げるとともに、胃は清潤を喜み脾は温燥を喜むという。
対立しつつ相互に滋済する生理的特徴を反映している。
ただし、腸道津枯はこの例に当てはまらず、滋膩の薬物を大量に用いるべきであるから、一般に論じない。
胃陰不足をひきおこす病機については、胃に着眼するだけでは十分でなく、肺腎両臓との関係を分析する必要があり、それによってはじめて胃陰不足に本質をとらえることができる。
水液の出入は肺・脾・腎の三臓と関係がり、三臓の間にも密接な関連があるためである。
外感温熱病では、温邪は上に受けまず肺を犯すので、熱盛傷陰を呈することが多いので、熱病後期の胃陰不足には、肺胃の陰を滋潤する沙参・麦門冬・玉竹・石斛などをよく用いる。
内傷による胃陰不足には腎陰虚をともなうことが多く、腎は主水の臓で五臓の陰は腎陰によって滋養されるために、腎陰が不足すると胃陰不足を引き起こすからである。それゆえ平素から胃陰不足を呈している時には、滋腎壮水の生地黄・玄参などを用いるのである。以上は、胃陰不足の病機の違いによる用薬の相違である。
熱病後期で余熱が残り胃津液がすでに衰えているとこは、養陰と清熱を同時に用いるのが良い。
「炉煙は熄むといえども、灰中に火あり」で、養陰だけで邪熱を再燃するのを防止できないからである。
方剤例⇒竹葉石膏湯・清暑益気湯
陰虚に湿熱を兼挟するときは、養陰と清熱利湿を同時に行うと良い。甘露飲に大量の養陰薬に清熱利湿の茵陳を配合しているのが、この例である。この種の方剤の構成は典型的な益胃生津法ではないが。啓発的にで実際に有用である。
本方と肺の清燥潤肺法は組み合わせの形式がよく似ており、肺の清燥潤肺法に宣降肺気の薬物が配合されていて肺の生理的特徴に配慮している点が異なる。
前に述べた運脾除湿・清熱祛湿・実脾利水・祛痰滌飲の四法は、脾運の障害による津液壅滞という病機に対する治法であり、本法は胃液消耗・陰津虧損に対する治法であるから、有余と不足で一対をなしている。前後を参照すると、津液に大過と不及が発生する病理変化を、全面的に認識し理解することができる。
ああ・・・記載されている内容がかっこ良すぎて全文を勢いで書いてしまいました。
やっぱこの方の物事を全面的に把握して、仕組みを理解する能力は天才的やわ。
とりあえず、今回はこのへんで、続く…
大阪の浪速区にあるミズホ薬店の店主。
お店にひきこもって漢方の勉強をしたり、漢方相談をしながら暮らしています。