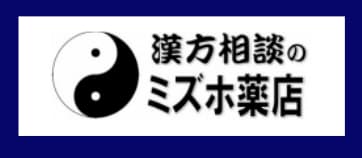脾陰虚と胃陰虚について(3)
2016年05月26日
引き続き、脾陰虚と胃陰虚について記載していきます。
胃は「水穀の海」といわれるように、その海の如く、摂取した食物を腐熟させ小腸、大腸で下向きに移動させる。
摂取した食物を腐熟(消化)させるのに海のような陰液が必要である。
(タプタプした水のイメージね。)
その海のようなタプタプした水の量が少ないと、摂取した食物を効率よく腐熟させ下向きに移動できないので、摂取した食物が胃の中に残り、便秘になり熱の原因になったり(これは承気湯証のような病機〉、または通常、胃の動きは下向きなのだが 、人間の体がその食物を口から排出しようと胃の動きが逆向きの上向きに変わるなどの症状が起こる。(食事をした後に吐き気がする、または戻してしまうなど)
中医学では何事も物事の根源を陰と陽という、ものさしで考えるので、上記の海のようなタプタプした水を陰と考えるなら、胃の活動は陽で、そのタプタプした水の量が減れば、陽(食物を腐熟させるエネルギー)の働きが強くなる。
この病機は胃 陰 虚で胃の陰が虚するという現象であり、その胃の陰が衰えていることにより胃の陽の働き(腐熟させるためのエネレギー)を抑えることができないので、余った熱が身体に異常をきたすのである。
その症状が胃陰虚の主症状である、口の渇き・口唇の乾燥・咽の乾燥・舌質が紅で乾燥・胃部の疼痛・便秘などである。
治療は、その不快な症状を解消するためには胃のタプタプした水を補ってあげれば、良いのである。
メインは補う薬なので熱を瀉す薬でなく、前回のブログに記載した養陰生津の沙参・麦門冬・玉竹・石斛・生地黄・玄参・西洋参・知母。梨汁・蔗漿達の登場である。
そして陳潮祖先生が言うように
「胃陰不足には、肺胃の陰を滋潤する沙参・麦門冬・玉竹・石斛などをよく用いる。内傷による胃陰不足には腎陰虚をともなうことが多く、腎は主水の臓で五臓の陰は腎陰によって滋養されるために、腎陰が不足すると胃陰不足を引き起こすからである。それゆえ平素から胃陰不足を呈しているときには、滋腎壮水の生地黄・玄参などを用いるのである。以上は、胃陰不足の病機の違いによる用薬の相違である。」
今回は腎陰が不足することにより胃陰不足は記載しないので、 沙参・麦門冬・玉竹・石斛について少し記載する。
これらの帰経(簡単にいうと生薬が作用する臓器)について見て欲しい
(中医臨床の中薬学抜粋〉
・沙参
(性味)甘・微苦・微寒
(帰経)肺・胃
(効能)清肺熱・養肺陰・養胃生津
・麦門冬
(性味)甘・微苦・微寒
(帰経)肺・心・胃
(効能)清熱潤肺・止咳・養胃生津・清心徐煩・潤腸通便
・玉竹
(性味)甘・微寒
(帰経)肺・胃
(効能〉養陰潤燥・生津止渇
・石斛
(性味)甘・寒
(帰経)肺・胃・腎
(効能〉養陰生津・養陰清熱・滋腎陰・明目強腰
てな感じで、これらの働きは胃の津液を生み出すことなどで、脾を潤すことはできないように思われる。
私の個人的な意見ではあるが、胃陰虚と脾陰虚をごっちゃまぜにしているような感覚をお持ちの方が多いように思われる。そして出てくる処方が麦門冬湯てな感じですかね!?
(まあ、このブログを記載しているのも自分への戒めでもあるのだが。)
そろそろ飽きてきましたので、今日はこの辺で終わりにします。
次回は麦門冬湯に含まれる麦門冬と半夏から記載していこうと思います。
続く…
大阪の浪速区にあるミズホ薬店の店主。
お店にひきこもって漢方の勉強をしたり、漢方相談をしながら暮らしています。