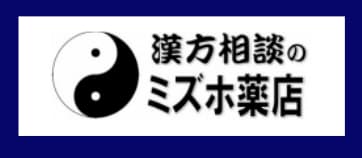脾陰虚と胃陰虚について(9)
2016年06月02日
脾陰虚に対応する参苓白朮散と胃陰虚に対応する麦門冬湯の方剤構成を比べてみます。
・参苓白朮散
人参9g・白朮9g・茯苓9g・炙甘草9g・山薬9g・白扁豆6g・蓮子4.5g・薏苡仁4.5g・砂仁4.5g・桔梗4.5g
・麦門冬湯
麦門冬15g・半夏4.5g・人参9g・甘草3g・粳米15g・大棗3g
この中で山薬・白扁豆・蓮子・薏苡仁・砂仁・桔梗と白朮・茯苓の作用に目を向けてみると
山薬⇒補脾止瀉・養陰扶脾・養肺益陰・止咳
白扁豆⇒消暑化湿・健脾化湿・解毒和中
蓮子⇒健脾止瀉・養心安神・益腎固精
薏苡仁⇒清利湿熱・祛湿徐痺・排膿消腫・健脾止瀉・脾陰滋補
砂仁⇒行気止痛・消食・開胃止嘔・温脾止瀉・理気安胎
桔梗⇒宣肺祛痰・排膿消腫・諸薬上浮
白朮⇒健脾益気・燥湿利水・固止汗・安胎・祛風湿
茯苓⇒利水滲湿・健脾補中・寧心安神
眺めてみると、脾陰を補うだけでなく止瀉や利水滲湿の薬効が目立ちます。
この事を踏まえた上で再度、金匱要略の条文に戻ります。
「問うて曰く、熱の上焦にあるのは、咳に因って肺痿となる。肺痿の病たる何よりこれを得るか。師曰く。或いは汗出てより、或いは嘔吐により、或いは消渇小便数より、或いは便難きより、また快薬を被り下利して、重ねて津液を亡う。故にこれを得る。曰く、寸口の脈数、その人口中かえって濁唾涎末あるは何ぞや。師曰く、肺痿の病たり。もし口中僻僻と燥き、咳けば、すなわち胸中隠隠と痛み、脈かえって滑数なるは、これ肺癰となす。咳して膿血唾し、脈数虚なるは肺痿なす。数実なるは肺癰となす。」
上焦部に起こった熱による咳の原因が、嘔吐、小便数、下痢による津液欠乏であると書かれている事と麦門冬湯の方意から参苓白朮散の方剤構成を読みとると、脾陰虚の場合は胃陰虚に比べると慢性的に続く下痢などから、表の腑ではなく裏の臓まで、もっと深い段階での津液欠乏が考えられる。
そのために、脾の機能を薬を補っていても、慢性的に続く下痢を止めない事には栓の抜けた風呂釜にどんどん水を足しているようなものなので止瀉の作用を持つ薬が必要なのだと考えられる。
脾は「万物が生じる土」なので、胃の水穀の海の水も脾から供給されているので、その土が弱り、適度な湿り気ではなく、バリバリに乾燥している状態では同時に胃陰虚も伴う事も考えられるが、以上の理由から脾陰虚の状態、万物が生じる土が乾燥している状態では麦門冬湯では当然改善できないのである。
そして利水滲湿作用が必要なのは、前回に記載したように脾気虚のため水穀の精微を完全なる気体状態まで変えることができない状態が長く続くために、万物が生じる土が部分的には泥のような状態になっている状態も考えられる。
以上、少し長くなりましたがとりあえず今回はこれで、脾陰虚と胃陰虚についての考察は終わりたいと思います。
私は修行中の身ですので、この考察についても順次、訂正&追加を行っていきます。
大阪の浪速区にあるミズホ薬店の店主。
お店にひきこもって漢方の勉強をしたり、漢方相談をしながら暮らしています。